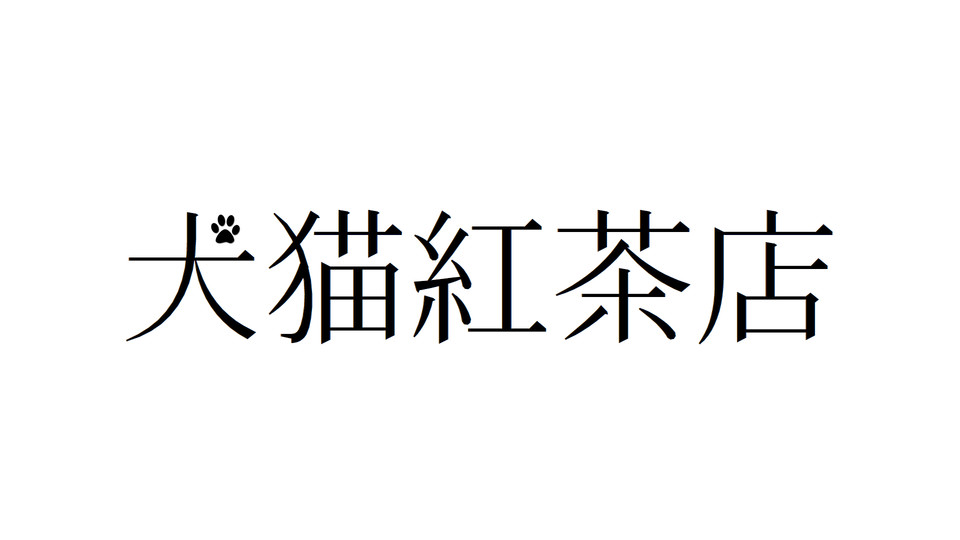2025/07/11 17:48
「風味」という言葉の意味を調べると、その例文に
「風味のよい紅茶」
なんて書いてあります。良いですね「風味のよい紅茶」
風味(フウミ)とは? コトバンク
肝心の意味はといえば、一番上にこう書いてあります。
1 飲食物の香りや味わい。「風味のよい紅茶」
うんうん。味や香り、さらには食感、場合によってはその飲食物の見た目なんかも含めて完成するのが「風味」というイメージがあります。
でも、ふと思うのですが、私たちは日頃の生活であまりこの「風味」という言葉を口にしません。
たとえば新商品のお菓子や飲み物が出た場合
たとえばどこかでおいしいものを食べたよという話をした場合
たとえばめずらしい料理の名前を聞いた場合
いずれも私たちの口をつくフレーズは
『どんな味?』
じゃないかなと思います。
「へー、おいしそう。どんな味なの?」
うん、めちゃくちゃ馴染みのあるフレーズです。
きっと紅茶だって、同じように「どんな味?」文脈で語られることが多いでしょう。
ここでちょっと立ち止まって考えてみたいのですが、本来「味」という言葉は舌が飲食物を通して感じるものを指す言葉です。「甘味・酸味・塩味・苦味・うま味」が基本味なんて言われたりしますね。そこには香りや食感は含まれません。まして見た目なんて入ろうはずがありません。辛味は基本味とは感じる仕組みが違うけど(舌の味蕾で感じるのではなく痛覚に近い感覚だと言われてますね)、これは入るのかな?
つまり私たちは「味」に香りや食感、見た目の印象などを付加したものを「味」と表現しているわけです。ややこしい!!

この小さな味と大きな味がごっちゃになると、たとえばお茶のブレンドをするときなどには困ります。
舌で感じる(小さな)味と鼻で感じる香り、それも湯気から直接鼻で感じる香りと、飲後に鼻腔に抜けるのを感じる香りがごっちゃになると、ブレンドづくりは大混乱しますし成り立ちません。
おそらくお茶に限ったことではなく、食をプロデュースするお仕事をされている方であれば、きっと同じことを思われることと思います。
(小さな)味と香りやその他の要素はしっかり分けることが大切です。
でもね、でもですよ、じゃあ、この「味」二重構造問題がネガティブかというと、決してそうでもないと思うんです。
たとえばさっき紹介したフレーズ。「どんな味?」をより正しく「どんな風味?」にしたらどうでしょう。
感じ方は人それぞれかなと思いますが、私はなんだか味気なく感じます。情緒のコミュニケーションよりも分析的な視点が重視されている印象になるっていうのかな。なんかちょっと冷たくなるような印象をおぼえます。
やっぱりそこは手軽に使える「(大きな)味」で会話することで、私たちの豊かなコミュニケーションが成り立っているような、そんな気がするのです。
言葉っておもしろいなって思います。
「味」と「風味」。「風」の一文字、[Fu:]という一音節([Fuu]の二音節??)で、対話の温度ががらっと変わる。
紅茶をはじめとするお茶は非常に奥深いものなので、「小さな味」や「(二種類の)香り」、「水色(すいしょく)」、あるいは容器だったり、茶葉や茶殻の色合い、形、いろいろいろいろなことを考えようと思えば考えられて、そこに面白さを感じることもあるでしょう。
けど手軽に楽しんだり、その楽しさを共有するには、やっぱり言葉が含む情報はシンプルな方があったかいのかもしれません。
「味」以外には、音楽には詳しくないけど「音」と「音色」の関係なんかも近い要素があるのかもしれませんね。
あとはいろいろなジャンルで「雰囲気」とか「感じ」が大きな意味で我々のコミュニケーションを支えてくれているのかな。
紅茶もその他の趣味も、私は日常的には大きく気楽に楽しめたらいいなと思います。